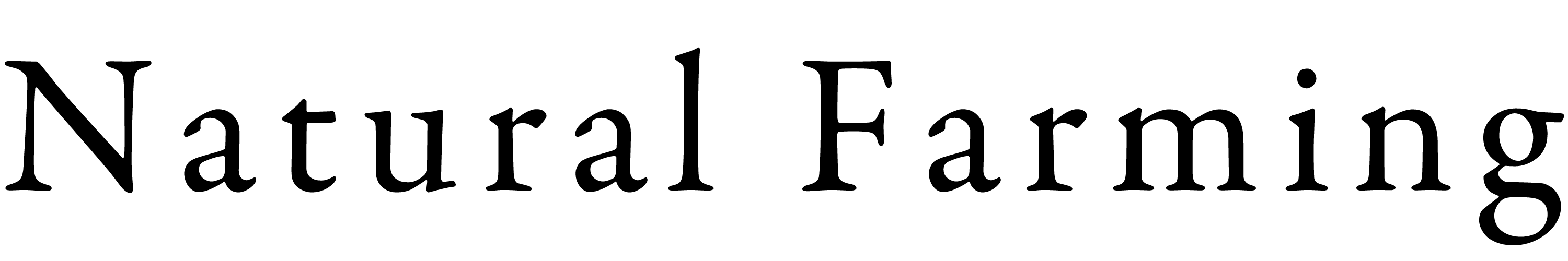2025/10/14 11:23

日本お米ばなし vol.69「お米の研ぎ方が正しいのか不安」
新米が出回るこの季節。店頭には新米入荷ののぼりが並び、「今年の新米、もう食べた?」という声も聞こえてきます。
そんな中で、意外と多いのが「お米の研ぎ方、これで合ってるのかな?」という質問です。親から教わった通りにやっているけれど、正しいか自信がない。そう感じている方は少なくありません。
お米の研ぎ方は、実は時代とともに変化しています。
昔と今では、お米そのものの状態も、精米技術も、家庭の水環境も違います。かつての「常識」が、今では逆効果になってしまうこともあるのです。
今日は、そんな“お米の研ぎ方の今昔”を、米屋の視点から紐解いてみましょう。

なぜお米は「研ぐ」と言うのか
そもそも「研ぐ」という言葉には、「磨いてつやを出す」という意味があります。
昔のお米は、現在のように精米機が高性能ではなかったため、ぬかが多く残っていました。そのため、手でしっかり擦り合わせてぬかを落とす必要があり、まさに“磨く”という作業だったのです。
ぬかが残ると、炊き上がりがべたついたり、香りが悪くなったりします。
そのため、昔の人は米をボウルの中でゴシゴシと力を入れて研ぎ、水を何度も替えて白く濁らなくなるまで洗っていました。
“お米を研ぐ”という行為には、暮らしの中の知恵が詰まっていたのです。
時代とともに変わったお米
一方、現代のお米はまったく違います。
精米技術の進化によって、ぬかの残りは非常に少なくなり、粒の表面は滑らかに整えられています。
つまり、昔のように力を入れて研ぐと、今度はお米の表面を傷つけてしまうのです。
傷がつくと、そこから旨み成分や香りが流れ出し、炊き上がりの食感も悪くなります。
また、水道水も昔とは違います。井戸水が主流だった時代と違い、今は塩素などの消毒成分が含まれています。お米は最初に触れた水を一番よく吸うため、最初の“すすぎ水”の扱いが非常に重要になってきました。
現代のお米の洗い方
では、いまの時代に合った「正しいお米の研ぎ方」とはどういうものなのでしょうか。
ポイントは、“研ぐ”ではなく“洗う”という意識です。
① 最初の水は10秒以内に捨てる
お米は水に触れた瞬間から吸水を始めます。最初の水はぬかの粉や微細な汚れを含むので、できるだけ手早く。水を入れたら2〜3回軽くかき混ぜ、すぐに捨てましょう。
※お米は最初に注いだ水をよく吸収してしまいますので、汚れた水を吸わないように手早く実施することがポイント!
② やさしく、空気を含ませるように混ぜる
次に、水をお米が浸かるくらいまで入れ、優しくかき混ぜ水を捨てます。強く握りつぶす必要はありません。
「お米を傷つけず、ぬかを落とす」感覚で。
③ 水を2〜3回替える
3回ほど繰り返すと、濁りがやや透明に変わってきます。完全に澄んだ水にする必要はありません。少し白く濁っているくらいが、旨みが残ってちょうどいいバランスです。
④ 夏場は短め、冬場はやや長めの浸水を
洗い終わったら、季節によって吸水時間を調整します。夏場は45分ほど、冬場は1時間を目安に。吸水が足りないと芯が残り、逆に長すぎるとべちゃつきます。
この洗い方を基本に、計量から炊飯までの流れは「お米の炊き方」でご紹介しています。
「昔の教え」は間違いではない
「研ぎすぎは良くない」と聞くと、つい昔の方法を否定したくなりますが、実はそうではありません。
昔のお米は今よりぬかが多く、精米も粗く、だからこそ力を入れて磨く必要がありました。
当時の人々の暮らしの中では、それが理にかなった方法だったのです。
つまり、お米の研ぎ方に“正解”はひとつではなく、時代ごとの最適解があるということ。
大切なのは、目の前のお米に合わせることです。
同じお米でも、銘柄や精米歩合、保存状態によって最適な洗い方は微妙に違います。
だからこそ、少しずつ感覚をつかんでいくことが、“お米上手”への第一歩なのです。
【まとめ】
・「研ぐ」は昔のぬか落とし、「洗う」は今の表面ケア。
・最初の水はすぐ捨て、2〜3回やさしくすすぐ。
・お米は時代とともに変わる。だから、研ぎ方も変わる。
おわりに
お客様とお話していると、「うちはずっとこうやってきたから」「細かいことはやっていられない」とおっしゃる方もいます。でも、ちょっとした洗い方の違いで、驚くほど味が変わるのが“お米の面白さ”です。
それに、現代の精米技術が向上したおかげで、力を入れてゴシゴシ洗ったり、何度も水を換えたりしなくてよくなっているので、お米の洗い方をアップデートした方がお客様にとってお得だと思っています。
とくに新米の季節は、粒の中にたっぷりと水分が含まれているため、やさしく扱うほど甘みが引き立ちます。
手早く、やさしく、そしてお米の声を聞くように。
今年の新米は、そんな気持ちで“研がずに洗う”を試してみてください。
お米の透明感と香りが、きっといつもよりふっくらと感じられるはずです。