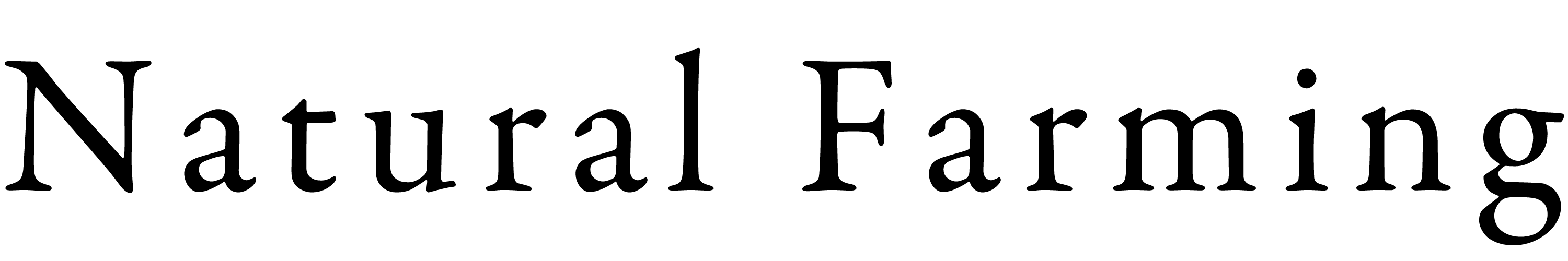2025/10/30 10:50

日本お米ばなし vol.70
「お米が値上がりと買い控えの先にあるもの」
待ちに待った新米の季節が到来しました。しかし、今年は農協の概算金が一気に上昇し、末端の販売価格も大幅に上昇しています。そのため、価格を優先する消費者の中には、お米の購入を控え、パンや麺類で代替しようとする動きが高まっています。
このような選択が農業や環境に与える影響について、私たちは今一度考える必要があります。
自然栽培米・有機栽培米の特徴と利点
自然栽培米は、化学肥料や農薬を使わず、土や微生物の力を最大限に活かして育てられるお米です。土壌の健康が保たれることで、生物多様性が維持され、作物自体も健やかに育ちます。例えば、自然栽培の田んぼでは微生物や小動物が活発に活動しており、これが土の栄養循環を促し、安定した収穫につながります。
一方、有機栽培米は、化学的な農薬や合成肥料を使わず、有機肥料を用いて栽培されるお米です。自然の力を活かす点では自然栽培米と共通していますが、認証制度に基づいて管理されるため、安全性や品質が保証されやすいのが特徴です。また、有機栽培では土づくりや病害虫管理が計画的に行われるため、持続可能な農業のモデルとしても注目されています。
どちらも、化学物質に頼らない栽培方法のため、環境への負荷が少なく、地球や地域社会に優しいお米と言えます。これらを選ぶことは、食べる人の健康への配慮だけでなく、持続可能な農業や環境保護への貢献にもつながるのです。
戦後の消費行動がもたらしたもの
令和の米騒動は、突然起こったことではなく、これまでの私たちの消費行動の積み重ねが引き起こした課題です。
戦後の日本では、高度経済成長とともに「パンや麺が新しい」「おかずを豪華に」という価値観が広まり、かつて主食の中心だったお米は、徐々に「ありふれた食品」へと位置づけが下がっていきました。
1962年をピークに国民1人あたりの米消費量は減少の一途をたどります。
代わって小麦を原料とする食品が食卓を占めるようになりました。
「主食を軽く、おかずを豊かに」。
それは当時、豊かさの象徴でした。
けれど半世紀を経た今、その行動の積み重ねが、いくつかの課題を生んでいます。
「安く・便利に」が当たり前になった結果
戦後の消費社会では、「大量生産・大量消費・低価格」が良いこととされました。農産物にもその波が押し寄せ、生産現場は価格競争に巻き込まれます。
少しでも安く届けるために、化学肥料や農薬への依存が進み、「土を育てる」という長期的な視点は後回しにされがちになりました。
また、便利さを追求する中で、炊飯や保存など「お米を扱う手間」も削られていきました。炊飯器が進化し、コンビニのおにぎりが普及した一方で、味噌づくりや漬物づくりなど、台所の知恵が少しずつ姿を消しました。
その結果、お米に限らずですが、「誰が、どこで、どんな思いで作っているのか」を考える機会が減り、“食べ物の背景”が見えにくくなったのです。
「顔の見える関係」の喪失
戦後、日本の人口の多くが都市へ移り住みました。
1950年には全国の人口の約半分が農村に暮らしていましたが、2020年には農林業従事者が総人口のわずか3%ほどにまで減少しています。
この急速な都市化は、食の「生産」と「消費」を分断しました。
戦前までは多くの人が農家や田んぼに直接関わり、「自分の食べるものを誰が作っているか」を自然に知っていました。
しかし、流通や販売が全国規模になったことで、スーパーの棚に並ぶお米は“産地名のついた商品”となり、生産者の顔や田んぼの風景が見えにくくなっていきます。
1990年代以降には、JAや大手流通を通じた集荷が一般化し、小さな地域の米屋や個人販売のルートが次々と姿を消しました。
農家と消費者が直接やりとりをする機会は激減し、「どこの誰がどんな思いで育てた米なのか」よりも、「どのブランド・どの等級か」が重視される時代になったのです。
こうして「うちの田んぼの米が一番うまい」と語り合う地域の誇りは、「有名産地の米を買う」消費行動へとすり替わりました。
多様な在来品種や地元独自の栽培法が失われたのも、この“顔の見えない時代”の副産物です。
それでも、変わり始めている
ここ数年、食を取り巻く意識は確実に変わり始めています。
内閣府の調査(2023年「食料・農業・農村に関する世論調査」)によると、
「国産農産物を積極的に選びたい」と答えた人は全体の73%にのぼります。
日本政策金融公庫が実施した「消費者動向調査(令和5年1月)」によると、食料品を購入するときに国産品かどうかを「気にかける」と回答した人のうち、 「安心・安全だと思うから」が75.9 % と最も高かったというデータがあります。
また、農林水産省の統計では、有機農産物の市場規模は10年間で約2倍(2009年約1300億円 → 2022年約2240億円[推計])に拡大しています。
この背景には、「環境負荷の少ない農業」「持続可能な食の仕組み」を支持する消費者が増えていることがあります。
お米においても、有機JAS認証米や自然栽培米を選ぶ層が年々増えており、
量よりも「誰がどのように作っているか」に価値を見出す動きが広がっています。
かつて“安さ”が第一だった市場に、いまは“信頼できる作り手から買う”という新しい基準が生まれつつあるのです。
「買い続ける」ことが未来を守る
農業の現場では、危機的な変化も起きています。
農林水産省によれば、基幹的農業従事者の平均年齢は68.4歳(2020年時点)。10年後には現役農家の半数が引退すると見込まれています。
つまり、消費者が国産米を選び続けなければ、田んぼの維持そのものが難しくなる地域も出てくるということです。
しかし逆に言えば、「お米を買う」ことは農地を守る直接的なアクションでもあるのです。
ざっくりな試算ではありますが、1世帯が年間60kgの国産米を買うと、約100㎡の田んぼの経済的維持に貢献していると考えることができます。
その田んぼは、水源涵養・生物多様性・洪水防止など、私たちの暮らしを支える多面的な機能を有しています。
つまり、消費者が米を選ぶ行為は、「地域の風景と生態系を支える投票」でもあるのです。
価格の変動にかかわらず、“顔の見える米”を買い続けることが、長い目で見て最も確かな「安全保障」につながります。
「お米を買う」という文化へ
私たちが効率と便利さの代わりに、消費行動で手放してきたものは、もしかすると“日本の食文化そのもの”だったのかもしれません。
しかし今、リスクや不安の多い時代だからこそ、再び“誰から買うか”を大切にする文化が芽吹いています。
近年、生協・CSA(地域支援型農業)・オンライン直販サイトなど、生産者と消費者がつながる仕組みは増加しています。
消費者が生産者のストーリーを知り、「この人の米を応援したい」と思って買う流れが、確実に定着し始めています。
お米を買うという行為は、もはや単なる“食材購入”ではありません。
それは、作り手と風景を選び取る文化的な営みです。
一粒の向こうにある努力や地域を想像しながら買うこと。
それこそが、これからの豊かさの形ではないでしょうか。
便利な暮らしの中で、かつて手放してしまった食とその未来を、もう一度私たちの手に取り戻す時が来ています。
おわりに
物価の上昇が続くなかで、お米だけが安価なままでいられる時代は終わりに近づいています。そもそもその価格では購入できないものを燃料や資材、物流コストの上昇に加え、生産者の高齢化と担い手不足が重なり、値上がりは避けられません。それでも「お米は安くて当たり前」という感覚が私たちの中に根強く残っています。
けれども、10kgを5000円で購入しても、1膳(150g)のごはんはおよそ75円。外で飲むコーヒー1杯よりも安い価格で、主食をまかなっています。もしそのコーヒーを週に数回だけ自宅で淹れるようにする、あるいはコンビニのスイーツを少し減らすなど、小さな習慣を変えるだけで、良質なお米を選び続ける余裕は生まれます。
「何を買うか」は「どんな社会を支えるか」という意思表示でもあります。お米を選ぶことは、単に食べるものを選ぶのではなく、その背景にある田んぼの風景や水の循環、地域の暮らしを選ぶことです。
節約の優先順位を見直すとき、削るべきはお米ではないのかもしれません。お米は私たちの食文化の中心であり、毎日の食卓を支える基盤です。少し高くても、信頼できるお米を買い続けることが、次の世代の田んぼと食を守ることにつながります。
小さな意識の変化が、やがて大きな支えになります。
お米を買い続けるという選択は、未来の日本の食卓を守る静かなアクションです。