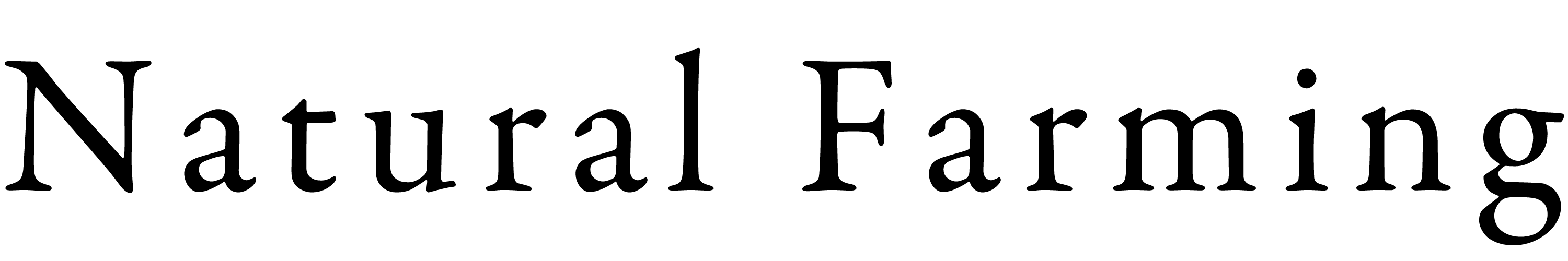2025/11/28 10:29

日本お米ばなし vol.71 「化学肥料の“ほぼ全量輸入”が示すもの」
Natural Farming — 化学農薬・化学肥料・家畜由来の堆肥を使わない米を選ぶ理由
日本国内の農業に使われる化学肥料。実はその原料のほぼ全量を海外に依存していることをご存じでしょうか。2025年10月に農林水産省がとりまとめた「肥料をめぐる事情」では、この輸入依存構造が改めて明確になり、業界関係者の間で注目を集めています。
窒素(尿素)、りん酸、加里(カリ)といった主要肥料の原料は国内では十分に確保できず、アンモニア、りん酸塩、塩化カリウムなどを海外から調達しているのが実情です。これは国際市場の価格変動や供給制約が、そのまま日本の米づくりのコストや安定性に跳ね返ることを意味します。
なぜこれが問題か
供給リスクと価格ショック
世界の資源動向、物流、地政学的リスクによって原料価格や輸入量は大きく変動します。近年の価格高騰は、肥料メーカーの調達コストと販売価格に直結し、多くの農家の経営を圧迫しています。
農家の経営と収量への影響
肥料コストが上がれば、散布量の最適化やコスト削減を迫られ、結果として収量や品質に影響する可能性が出てきます。これが流通や最終的な消費者価格へ波及します。
環境・土壌の長期健全性
化学肥料の多用は、土壌中の微生物バランスや物理性を変え、長期的な地力の低下につながる恐れがあります。一方で、有機栽培や自然栽培は、生物多様性の向上や土壌微生物群集の回復効果が、数多くの国内外の研究で示されています。
加えて、輸入相手国が特定国に偏っていることも潜在的なリスクです。さらに、りん安を含むりん資材の価格上昇が続いており、安定供給に対する懸念は深まっています。
私たちが「化学農薬・化学肥料・家畜由来の堆肥を使わない」お米を扱う理由
Natural Farming は、ただ「有機である」「無農薬である」というラベルを掲げるだけではありません。地域資源を活かし、土が本来持つ力を取り戻すことで、外部資源への依存を減らし、持続可能な米づくりを実現することを目的としています。
輸入依存リスクの軽減
肥料原料の海外依存は価格や供給のショックを招きやすい。自然栽培はその影響を受けにくい生産体系を育てます。
土壌と生態系の回復
化学投入を抑えることで、土壌中の微生物多様性が高まり、水分保持や養分循環が改善します。干ばつや豪雨といった気候変動への対応力も高まるとされています。特に、有機農業の生物多様性への貢献は、多くの研究で実証されています。
地域循環型の価値創出
稲わら・米ぬか・地域の緑肥など、現場で循環できる資源を生かすことで、農家の経営安定や地域内経済の循環につながります。国内での肥料自給や資源循環は、政策的にも重要なテーマになっています。
なお、家畜由来の堆肥は国内のりん循環を支える上で重要ですが、飼料自給率が26%と低く、堆肥であっても多くが海外由来の資源に依存しているのが現実です。
2030年までに化学肥料20%低減へ
慣行農業と有機農業はしばしば対立的に語られますが、本来は「生産性」と「環境配慮」の両立を図るための選択肢であり、二者択一ではありません。
「食糧生産に不可欠な化学肥料のほぼ全量を輸入に頼っている」現実を踏まえると、国内資源を最大限活用し、外部依存を減らす方向性は不可避です。令和4年度には肥料価格高騰対策の中で政策目標として、2030年までに化学肥料の使用量20%低減が掲げられました。
生産者を「慣行」「有機」と大きく区切るのではなく、どの農法であれ国内資源を活かし、持続可能な農業をどう実現するかという視点が求められています。
Natural Farmingのつくり手は、原料の多くを国内資源でまかなっていますが、農機燃料や一部資材には輸入に依存するものも残っています。ゼロか百かではなく、外部依存をできる限り減らす努力を続ける先駆者たちを支えることには大きな意味があります。
消費者にとっての意味
食の選択は生産の選択につながります。Natural Farming で扱うお米を選ぶことは、単に「安全・安心」だけでなく、日本の農業を輸入依存から脱却させ、土壌と地域資源を回復する方法をともに模索することでもあります。
即効性のある解決策はなくとも、持続可能性を優先する選択が、次世代の田んぼと食卓を守ることにつながります。
おわりに
Natural Farming のつくり手たちは、自然栽培や有機栽培という手法を通じて、化学肥料への依存から距離を置き、地域にある資源を活かしながら高品質なお米を届ける取り組みを続けてきました。ときに「オーガニックには興味がない」と言われることもありますが、化学肥料の原料をほぼ全量輸入に頼るという現実を前にすると、食と農の持続可能性を社会全体で考える必要性が浮き彫りになります。
この構造的な課題がすぐに解消されるわけではありません。しかし、地域資源を循環させ、外部ショックに強い生産体系を増やしていくことは、日本の食の安全性と持続性を確実に高める一歩になります。私たちは、その歩みをつくり手と消費者の双方とともに進めていきたいと考えています。